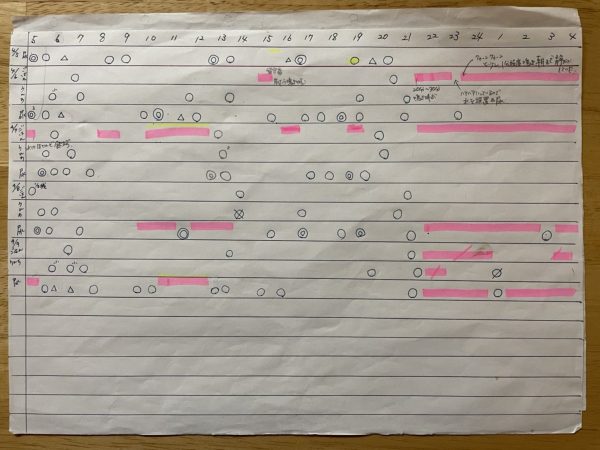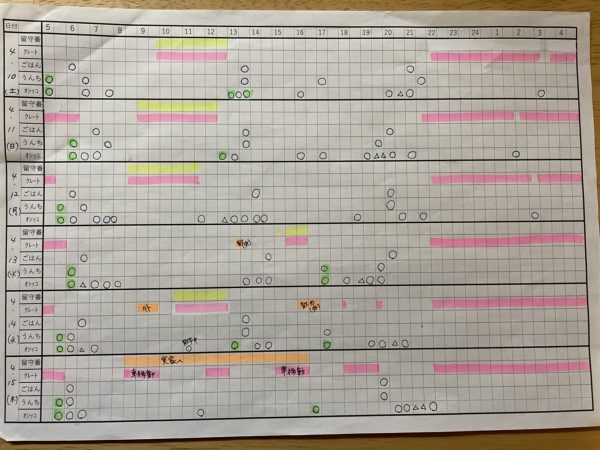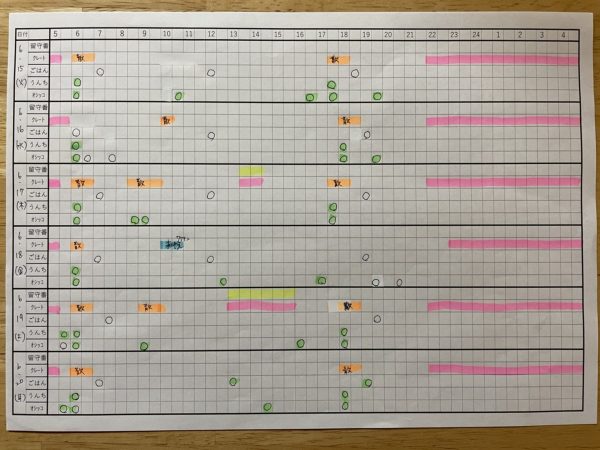グッドボーイハートではおすすめのベッドといえば、あの高価なエルエルビーンのベッドです。
あまりにも高値のために別ブランドのベッドで試した結果、結局エルエルビーンにたどり着いたという飼い主さんもいます。
「買う」と決めたけど難しいのはサイズ選びです。
どのサイズがおすすめですか?
と聞かれることもあるのですが、大きい方がいいのか、小さめがいいのか、犬にもよるしお部屋のサイズのこともあります。
また子犬のときだったら少し大きなものを買う必要がありますね。
参考にと、生徒さんたちからご提供いただいた犬用ベッドの写真をアップしておきます。
お部屋に応じて大小を使っている犬ちゃんもいます。

Mサイズリビング用
コーギーのメイちゃんは2台持ち。
リビングには大きなサイズを利用しています。
よくゴロゴロと転がっていて、大きいものにしてよかったと言われています。

寝室用にSサイズのベッド
寝室の冬用にはSサイズを利用しています。
丸くなって寝るのにちょうどよいらしいです。

Sサイズ 体重は6キロ
ジャックラッセルテリアのダンちゃんは、過去に準備したベッドをボロボロに噛みちぎり振り回した結果、エルエルビーンのベッドをついにかってもらいました。
ベッドの下のベッド台はお父さんの手作りですね。素敵!
「なんで、このベッドだけ噛まないの?」の質問に、エルエルビーンさんからの返答が欲しいですね。

Sサイズでダブル
2頭でお揃いの色のSサイズのベッドです。
刺繍はブランドでしてくれるのですが、モモちゃん、ネネちゃんはお母さんに刺繍をはってもらいました。
来客のときには各自のベッドで寝ています。

Mサイズ 子犬から成犬まで
子犬のときのはるちゃん。
大きくなっても使えるようにとMサイズを購入されましたが、大きく育ったので良かったです。

Sサイズの端っこにいます
ミニチュアダックスのモナカちゃん。
小さなベッドを振り回していたのでLLビーンを買ってもらいました。
このベッドも持ち運びにチャレンジしていましたが最近はよく寝ているようです。

Sサイズのベッドを愛用するサクちゃん
かなり年期がはいっているお気に入りのベッドに寝るサクちゃん。
購入してすぐに利用しなかったのですが、慣れてくるとこちらが気に入ったようです。自分仕様になっていて居心地がよさそうですね。
お留守番中はよくここにいるそうです。(カメラで確認)

Lサイズ ゴールデンリトリバー
クールちゃんは、最初は円形のベッドを利用していましたが、今そのベッドは寝室に移動になり、リビングにはLサイズのベッドで寝ています。
顔をこすりつけているらしいです。

Lサイズ ラブラドルリトリバー
黒ラブのメイちゃんはベッドの上で木をかじっていることが多いですね。
ベッドというとすごい速さで移動するのはさすがにラブですね。
サイズ感つかめたでしょうか。
小さな犬と大きな犬はあまり迷いがないでしょうが、中型犬が一番迷うところでしょう。
迷ったらひとつ上のサイズ選択がおすすめかもしれません。
お値段の高いベッドですが、子犬のころに買っておけばずっと使えるのですから、値段相応の価値はあるかと思います。
関連ブログ記事↓
<おすすめのアイテム>私が犬なら絶対におねだりするベッド:LLビーンの犬用ベッドがお買い得!
<おすすめのアイテム>犬用ベッドを考えるとき、しつこいようですが絶対におすすめするLLビーンの犬用ベッド