トレッキングクラスの報告が多くなっています。
クラス数としては圧倒的に家庭訪問トレッキングクラスが多いのですが、個人情報に触れることもあるので掲載を控えています。
トレッキングクラスもブログ掲載遠慮したいと希望者される場合はアップしていません。
ただ今のところ、トレッキングのご紹介を断られたことはありません。
トレッキングクラスに参加している生後さんたちは、家庭訪問で基礎のしつけをしてきた方々です。
グッドボーイハートの目標やこのブログの目指すところもご理解いただいているのだと勝手に思っています。
今回トレッキングクラスに参加してくれた保護された犬ちゃん。
この日トレッキングクラスとしてはひとつのステップを上がる管理方法に切り替えてみました。
犬の行動が安定したら管理を緩める
これは、犬のトレーニングの基本です。
トレッキングもはじめはこんなにきっちりと管理するのかと思うほどです。
トレッキングを犬を山に放たれると勘違いされている方もいますが、
トレッキング、つまり犬との山歩きほど犬に自制心と秩序を教えられる環境はえりません。
犬に目的を持って犬の行動を管理しながらトレッキングクラスを進めると飼い主の予想以上の行動が引き出せます。
この日もひとつのステップを上がった犬ちゃんの姿を観ることができました。
犬との暮らしで楽しいことはたくさんありすぎますが、喜びと言えば犬が心に安らぎや癒しの時間を取り戻した時です。
その土台はやはり家庭での過ごし方です。
あの家庭でのトレーニングのクラスがあったから今のこの山の時間があるのです。
飼い主さんは頑張られたのだなと、それも大きなよろこびになりました。
いつもありがとうございます。

Author Archives: miyatake
<クラスのこと>トレッキングクラスで犬の成長を観る喜び
<クラスのこと>「初めてのトレッキングクラス」開催しました
福岡では酷暑の犬たちもくたくたになっていますね。
山は季節の流れがはやくてもう秋の気配が漂っています。
はじめてのトレッキングクラスが開催される日は天候がとても心配ですが今回も最高のお天気に恵まれました。
はじめて七山のグッドボーイハートに来た生徒さんたちの感想は「相当の山ですね」。
ほとんどの方が思っていた以上の「山」であることにびっくりされます。
みなさんはグッドボーイハートが唐津に平地の田舎にあると思っているようですが、七山の池原といえば唐津市の中でも一番標高の高いところです。
その分風の通りもよく冷たい風が心地よく流れています。
今回のはじめてのトレッキングクラスに参加してくれた犬くんは山に来たのもはじめて。
生後9ケ月の若さ溢れるやんちゃ盛りの男のコです。
いろんな臭いに興味があって興奮しているように見えるのですが、いろんな臭いを嗅ぐこともできはいほどはじめは興奮しています。
山は全部坂道です。
坂の途中で止まると不安定になってじっとしていることができません。
飼い主さんの方もまだバランスがうまく取れないのでお互いがふらふらと…。
そのうちに安定してくると地面の臭いを嗅ぐ、そして急に動こうとするを繰り返します。
トレッキングに慣れている犬たちの行動とは比較になりません。
リードを持っていてもほとんどもっていないかのようにリラックスして歩かせることの難しさを体験していただきました。
自分さえしっかりとしていれば、犬は次第にバランスを取り戻しそのうちにリードはたるみます。
クラス中も飼い主さんと私ではリードを持つ人によって犬の行動が激変するのを見て飼い主さんは驚いていました。
解決のヒントは犬に求めるのではなく犬のリードを持っている自分にあるということです。
これは犬のしつけや犬との関係作りにおいても重要なことです。
犬に言うことをきいてほしい、落ち着いた犬になってほしいと思うことは構いません。
でも犬の行動を改善していくのに犬にばかり求めても何も変わらないのです。
犬はただ今起きている状態を素直に受け取って返しているだけなのです。
犬は本当にシンプルに表現してくれるすばらしい動物です。
近くにお山があるとのこと、練習してまたクラスにご参加いただくことになりました。
次回のトレッキングクラスがとても楽しみです。
みなさん犬について深い学びをされています。
グッドボーイハートをやってきて良かったと思う瞬間でした。

<本の紹介>自然治癒力を考える本「精神科養生のコツ」神田橋條治著
「精神科養生のコツ」はやさしく面白い本
久しぶりにおすすめの本の紹介です。
先日からブログに投稿させていただいた「自然治癒力」を学ぶために愛読している本をご紹介します。
神田橋條治先生の「精神科養生のコツ」です。
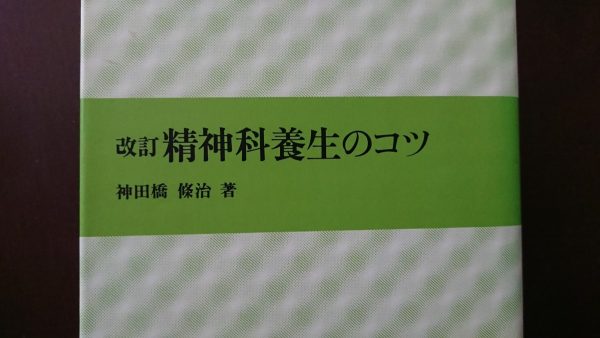
書籍の表紙や題名はいかにも精神科医の先生方が手に取られるような重厚な感じです。
しかし中身は大変シンプルな内容です。
一部をブログ記事でも紹介しましたのでご覧ください。
<犬・自然のこと>犬の自然治癒力を考えるために自分の自然治癒力を考える
神田橋條治先生は九州大学医学部出身なので地域的に親しみを感じました。
一般の方を対象に書かれたものと思われるほど、やさしく分かりやすい文章です。
しかも、自然治癒力を大切にするための自分が試せる具体的な方法が掲載されています。
その内容には科学的な根拠のないものもありますが、試してみても副作用のないものばかりです。
やってみて気持ちが良ければ続ければよい、それが先生のお考えのように受け取りました。
私が自然治癒力を学ぶことになった理由
犬の自然治癒力については、動物病院や食の専門家などいろいろな犬のプロフェッショナルの先生方がそれぞれの立場で考察されたものがあります。
家庭犬インストラクターとしての自分が犬の自然治癒力について学ぶようになったきっかけは、その職業としてではなくむしろ一飼い主としての立場からでした。
福岡市の博多駅近くにドッグスクールを構え、休みなく犬のトレーニングやドッグデイケアなどの犬のしつけのためにできることを取り組みました。
その間、共に暮らしていた愛犬は私の仕事の手伝いに付き合わされて消耗していきました。
そのことに気づいたのは彼が最後のメッセージを表情にして訴えたときでした。
約束を果たさねばと思い、山の中にある家(現在の七山のグッドボーイハートです)を見つけてオポを移動させました。
そこで自然治癒力に任せて元気になるなどという妄想は抱いていません。
ただ、自分は飼い主としてオポという犬と約束した「山に暮らそう」を彼の命のあるうちに果たしたかっただけです。
そのうち自然の空気と土と臭いの中で、消耗した犬は元気になってきました。
ただ健康になっただけではなく、それまで都会で見ることのなかった行動をたくさん見ることができました。
このことが今のグッドボーイハートの犬のトレーニングの基盤を固めたものになりました。
犬の自然治癒力にこだわる理由
自然治癒力というのはツールとして使われてしまうことがあります。
ツールとして使った方が、取り入れやすいし説明しやすいからではないかと思います。
どんな食事を与えた方がいいとか、どんなサプリメントがいいとか、どんなマッサージがいいとか、これはすべてひとつの形です。
目に見えないものに取り組むのにツールはとても便利です。
ただ間違えないようにしたいのは、これらは犬をただ長生きさせるための手段ではないということです。
より良く生きる時間を増やすためのお手伝いくらいが良いでしょう。
長生きを目標にすると長生きしなければ合わなかった、良くなかったと後悔が残ります。
では犬が長生きするとは何歳のことを言うのでしょうか。
10歳と思う人、12歳と思う人、15歳と思う人。
でも犬自身はどう思っているのかわかりません。
動物の生きる時間は人の生きる時間と同じように、豊かでリラックスしていて心から喜べる時間であるようにそばにいる飼い主が手伝えればと思うのです。
犬に何かをさせるためのしつけやトレーニングが犬に負担をかけるように、犬を健康にさせるための方法はやはり犬に負担をかけます。
犬のことを考えるなら犬は今どう過ごしているのかを見てあげるのが一番です。
犬が美味しそうにゴハンを食べていればそれが一番です。
心から解放されて満たされた時間が続けば、そのうち犬は自然とのつながりという奥深いものに犬が入る時間を得られます。
それは一瞬かもしれないけれど、神田橋先生の言われるとおりにとても気持ちの良い感覚なのだと思います。
そしてそのときに飼い主として一緒にそばにいることができれば本当にラッキーです。
神田橋先生の不思議な本。
もし読まれる方がいたら感想を教えてください。
グッドボーイハートのこだわりの本棚はこちらからどうぞ。
<受講生のコトバ・ディーノちゃん編>犬が犬本来の姿を取り戻すことができるためなら飼い主は絶対に頑張る!
クラスを受講して下さった生徒さんからいただいた感想文を掲載します。
今回はボーダーコリーの3歳のオス犬のディーノくんの飼い主さんからいただきました。
同居犬のナノちゃんもお写真に登場しています。
ではこちらからどうぞ・・・・・・・・・・・・・・
私がGoodBoyHeart(グッドボーイハート)の宮武先生に出会ったのは、
当時3歳ボーダーコリーが病気になり、
先生とともに頑張ろう!と思い、

ディーノくんとナノちゃん
先代の犬から10数年ともにドックスポーツを楽しみ、
でも、
決して甘やかすことはなく、

先生の知識はとても深く、多岐に渡り、私たちは、毎週、

犬たちが変わっていく姿がモチベーションとなり、

まだまだ続く犬との生活、より豊かな時間を過ごすために、
「
先生、

ここまで・・・・・・・・・・・・・・
グッドボーイハートにはいろんな行動のご相談があります。
吠える、噛みつくといった犬の問題行動の他に、犬自身がコントロールできない行動についてのご相談も多くあります。
ディーノくんの状態はそうした状態でした。
犬がセルフコントロールを失う状態には病名がつくことがあります。
投薬の必要があったとしても行動がゼロになることはなくどう犬につきあっていったらいいのか悩まれることも多いでしょう。
迷ったときは基本に戻ろうが犬についての真実です。
まず犬という動物の習性をもういちど素のところから勉強すること。
ディーノくんの飼い主さんにカウンセリングでお話したのはそんなことだったと思います。
私はいつも「こうしたらよくなる」「いつまでに改善する」とは言いません。
あなたが見ていることはこう、でも私ならこう見ると言えるくらいです。
そして犬という動物がどういう動物で何を求めているのかを知ること、それが本当に自分の犬を知るということだということをみなさんにお話しします。
今まで犬たちの幸せを考えて真剣に取り組まれたディーノくんの飼い主さんだからこそ私のど真ん中直球をちゃんと受け止めて下さったのだとこちらも感謝しています。
犬に何が起きているのか分からないといって、犬の脳を切り開いてみても何も出てきません。
でも犬に行動が起きている限り、どんなに小さな行動でもその中から真実を探す手がかりはあります。
そこに近付いていくためには、飼い主自身が変わっていく必要があるのです。
そしてその自分の変化が犬という動物に一歩近づけたのだと感じられるようになると、きっとはまります!
でもその興味は、犬を楽しむ道具として見る興味ではないのです。
その興味は犬を人の友達として知るという興味であり、愛したいという理解の始まりです。
ディーノくんのこと、ナノちゃんのこと、これからもっと知られることでしょう。
犬の世界にはまる楽しみ、犬たちと共に歩きながら体験していってくださいね。
<犬のこと>サンフランシスコの犬のトイレ事情を現地の飼い主さんから聞きました!
犬の排泄場所をどこにしていますか?
犬の排泄場所をどこに設置するかでいつも飼い主さんとの話し合いになります。
犬の習性を生かし自律した精神を養いたいなら、犬の排泄場所は屋外以外考えられません。
庭がないならベランダかバルコニーに、あとは散歩のときに排泄のチャンスを与えるなどです。
しかし日本には犬に室内で排泄をさせたいという人側の強い希望があります。
飼い主も庭ではさせたくない、なぜなら脚が汚れるから。
地域の人はもちろん犬の排泄を道路でも公園でもしてほしくない、なぜなら臭いから。
結果として犬は室内の犬用ペットシーツの上で排泄をすることを教えられほとんどの犬はそうするようになっています。
でもいつも思うのですが、犬を室内で飼う文化の長い欧米ではこの室内トイレ習慣がありません。
その生の声を生徒さんのお友達関係でアメリカのサンフランシスコ在中の方が犬の飼い主にインタビューしてひろってくださいました。
ブログ公開の許可を得ましたのでこちらからご紹介します。
サンフランシスコの犬のトイレ事情
~犬は室内では排泄しない~
ある犬の飼い主に犬のトイレをどうしているかを尋ねたところこんな答えが返ってきました。
おしっこと散歩の為に、1日に最低でも2回は屋外へ出ます。
玄関を出る寸前で、間に合わない時はそこでしちゃうこともありますが…。
たまにはエレベーターの中でもトイレの失敗をすることがあるのです。
でもきちんと訓練された犬なら公園で排泄します。
しつけをされていない犬がアメリカにたくさんいることは昔アメリカ在中のドッグトレーナーの講演で聴いたことがあります。
アメリカの犬の保護施設に犬が連れてこられる理由の一番は「排泄の失敗」だということでした。
私の友人の犬は、どの犬でも屋外で排泄します。
私の住むマンションでは、女性の人数よりも犬の数の方が多いくらいです。
犬はかなり賢くて、尿がしたくなると玄関のドアに行って教えてくれます。
そうは言っても、犬がもし不調だったりすると家の中ですることもあるのは確かです。
でも、室内の犬用のトイレの事は、聞いたことも見た事もありません。
聞いたところによると、犬は飼い主の庭では絶対に糞をしない。
また、ほとんどの犬はドッグフードを食べています。
猫を飼っている友人がいて、猫はおしっこや糞をそれ用のトイレでしているそうです。
猫については日本の室内飼育の猫と同じですね。
今朝散歩にでかけたら犬を連れて散歩をしている人達を見かけたのである女性に「
家に犬用のトイレがあるか」と尋ねてみました。
彼女の答えは「もしそれを持っていたら、 こうやってウンチをさせるために外に出たりしないわ」でした。
もう一人の女性にも聞いてみた。
「犬を飼っている人の多くは、犬が外で用を足すようになるまで、 家にウォーターマットを置いているのよ」と。
※ウォーターマットではなくウェットマットという防水シーツのことのようです!
犬を散歩させている人は、
袋を犬の鎖にくっつけて歩いているのをよく見かけます。 私が思うに、もし犬の糞の始末をしなかったら、 罰金刑があるんじゃないかと思います。
今日うちのエレベーターの中である住人の女性に「犬の下の世話をどうしてる?」って聞いてみました。
私達の住居にはみんなバルコニーが付いてるから、その女性が言うには彼女の犬専用のコーナーをバルコニーに作って犬は夜の間はそこを使っているみたいです。
私自身いなかに住んでいたんだけど、犬はどれもいつも外で飼ってありました。
犬が室内に入ることを許されていたときに、ならんかの理由で外に行くことがあれば、犬はただ玄関前にいって誰かがそのドアを開けれくれるのを待っているものです。
犬って家の中にはいりたくなるまで、ずーっと戸外にいます。
犬が家にはいりたい合図は、脚や頭をドアに軽く打ち付けれて知らせてましたね。
犬は大半の時間を庭や屋外で過ごし休憩したくなったら室内に戻ってくる、犬にとっては室内は安全に休める場所であって、走り回って遊ぶ場ではないようです。
サンフランシスコに限らずニューヨークやシカゴなどの都会を除くほとんどの家は、日本の家の数倍の広さです。
囲いのない家も多いのですが、囲いがしてあると犬を飼っているなというメッセージでもあります。
囲いを作ると土地を守ろうとするので番犬にはなるわけです。
日本ではそもそも犬を飼う環境が整っていない中で犬を飼う人を増やそうという力が働いて一気に犬の数が増えました。
ほとんどのマンションがペット可になりましたが、20年前には考えられないことです。
その分犬は小型化され室内トイレとサークルが常識となりました。
すべて犬という動物の習性を崩す恐れのあることばかりです。
気付いた人から考える、今はこれしかありません。
庭やテラスやバルコニーなどのベランダというものを持っているなら、犬にとって適切な場所で排泄ができるように犬を正しくしつけましょう。
今回は貴重なサンフランシスコの生の声をいただきありがとうございました!

<犬・自然のこと>犬の自然治癒力を考えるために自分の自然治癒力を考える
ドッグトレーニングなのに犬の自然治癒力に注目している理由
犬のトレーニングなのになぜ?と思うかもしれませんが、自然治癒力は体の病気の治癒のはなしでは収まりません。
自然治癒力というのは病気のことだけでなく、精神的な傷の治癒力にも関係するからです。
犬のトレーニングの依頼には、吠えること、噛みつくことといった具体的な問題行動の他に、パニック症、不安行動、多動、異常行動、恐怖症、コミュニケーション障害といった症状が行動として現れていることもたくさんあるのです。
症状によっては犬の精神の一部が損傷を受けているわけなので、それが自然に治癒されるのにどのような環境とどのくらいの時間が必要なのだろうかと考えるからです。
今日は自然治癒力を考えるにあたって、自分の自然治癒力に関心を持っていただくことで話を広げていきたいと思います。
神田橋先生の書生から自然治癒力の働きについて学ぶ
そこでまた転載させていただく資料が神田橋條治先生の書籍「精神科養生のコツ」です。
同書の53ページ第四章「自然治癒力の働きを見つける」から転載します。
ここから…
いのちは、よくない状態から回復するためのいろいろな方法を、自然にもっているのです。
これが自然治癒力です。
病気のときには、必ず自然治癒力が働きます。
いのちが病気をなんとかしようとするからです。
ここまで…
神田橋先生の適格な自然治癒力の説明については先日のブログでも転載で紹介しました。
簡単にはこのような説明なのですが、病気はそう簡単にはなおりません。
自然治癒力が働いてすぐに勝手に治癒が進むのなら、医療はここまで発展しなかったでしょう。
草刈り中におきた小さな切り傷は放置しておけばそのうちに治癒しますが、
激しく損傷した傷は手術を受けないと治癒せずに悪化してしまうこともあります。
それだけでなく、自然治癒力というのは悪い状態から回復する段階では、いろいろ難点があるのです。
神田橋先生は同書にこのようにまとめられました。
ここから転載
まず第一に、症状は不快であるという点です。
症状を消したり軽くしたりするほうが「気持ちがいい」のです。
ですから熱が出ると熱を下げたり、痛みには鎮痛剤を飲んだりするのです。
第二は、症状が生活の妨げになるという点です。
また、熱が出て食欲がないので食事をしないと、体が弱ることもあります。
生活のためには、吐き気を薬で押さえて出勤しなければならないことも多いでしょう。
第三は、自然治癒力の作用は、少し遅れて始まり、少し遅れて終了するという点です。
ですから、もう胃の中がカラッポになっても、ムカムカ感や吐く動作は続くのです。
そのときにはもう、吐く動作のようはすんでいるわけですから、止めた方がつごうは良いわけです。
最後に第四点として、症状の中にある自然治癒力の働きについては、医学の世界でまだまだ新しい発見が続いているという点です。
いま行われている症状を止める治療が自然治癒力を邪魔していることが分かってくるかもしれません。
ここまで転載…
転載が長くなりましたが黒字が要約です。
要するに自然治癒力は、不快で、生活の妨げになることもあり、遅れて始まり、働きについてはまだ明らかにされていない、と不安定な要素が満載なのです。
「絶対に治ります」という言葉は医療現場では患者には言わない言葉だと聞いたことがありますが、自然治癒力の働きや作用は完治の保証もないもっと分からないものでつかみどころがないものだけにどうつきあえばいいのか不安になります。
自然治癒力に頼って本当に治るのだろうかと不安を抱えてしまうのも仕方ありません。
さらに治癒が働く際の自分の中に起きる気持ちの悪い変化に注目して過ごすのはなかなか難しいことです。
自分の内側に注目することで自然治癒力を感じることができる
でも自分が望んでも望まなくても個々の動物の中には自然に自然治癒力が働くシステムになっています。
どうやったって毎日このことが自分の中に起きているのだから、積極的に付き合った方が良いと私は思うのです。
自分の中に起きていることに注意を向けることで自然治癒力が今働いているかどうかを知ることができるということなので、これだけでもまずは習慣づけたいと自分の内側で起きていることに注意を払う習慣をつけています。
実はこのことに関して犬は圧倒的に人よりも勝っています。
犬は良い意味で自己中心的なのです。
自己中心的とは自分勝手に要求するということではありません。
自分に起きていることを一番大切にするということです。
そのため、環境が整っていないとか、自分の発達が追い付かず環境の中に安心を得られないと感じるとすぐに行動として表現してくれます。
犬は自分の中に違和感を覚えるとすぐに飛びついたり、噛んだり、吠えたり、走り回ったりといった興奮行動や攻撃行動をしてくれます。
犬は自分の内面に起きていることをちゃんと表現できるとても分かりやすい動物なのです。
ということは犬は自然治癒力が自分の中に働いているときにもすぐに行動に示します。
それは自然治癒力の操作としておきる「気持ちが悪い」という行動もたくさん入っています。
ヒトにからみると明らかに具合が悪そうな犬。
飼い主としては見過ごすこともできない気持ちもよくわかります。
下痢は止めたいし、咳も止めたいし、熱も下げたいし、震えも止めたいし、かゆみも止めたいです。
すぐに医学的な処置が与えられるでしょう。
外飼いの犬の場合には人に気づかれることがなく、少しの不具合は自然治癒力で解決していたことも、室内の犬となると飼い主の気づきも早くまたどこまでを見守っていいかがわからず手の出し方も微妙な感じになっていきます。
犬に起きている自然治癒についてわからないことばかりですが、まずは自分の中に起きていることをわかるようになることが先です。
もう少し勉強したいという方は神田橋先生の書籍「精神養生のコツ」を読んでください。
とても役立つ日々できる自然治癒力を感じる方法がたくさん書いてあります。
神田橋先生は自然治癒力を治療を考えず、養生と考えて取り組むことをすすめられています。
近々goodboyheartの本棚にもアップしておきます。
犬をなでて気持ちがいいだけでは本当の治癒にはならない
最後になりましたが大切なこと。
犬をなでたり触ることで人は「気持ちがいい」感覚を得ることができます。
これが人のいう「犬に癒される」という感覚です。
アニマルセラピーはこの「動物から癒される」効果を活用したセラピー活動です。
でも神田橋先生の書籍の中にもたくさん登場するとおり、本当の根の治癒は「気持ちがいい」という快楽だけでは終わりません。
気持ちがいいと一瞬癒されてもまた人は次のストレスをためてしまい、毎日犬に触って気持ちがいい繰り返すことは犬に負担をかけていることもあるのです。
触られる犬の方がどんどん落ち着かない感じになっているのなら、触れることも負担になることがあると受け取り別の「気持ちがいい」環境を探しておきましょう。
人が癒されたいと思っている以上に、犬も自然の力による治癒を必要としています。
だからいっしょに自然の中のもっと大きなエネルギーの中に入っていくために、犬との山歩きおすすめしています。
9月から多少昆虫たちがワイワイしますが秋はトレッキングに最も適した季節です。
ぜひ山歩きを習得して犬と共に癒される空間を見つけてください。

<犬・自然のこと>犬の自然治癒力って何だろう?を考える
※部分追記しています。
昨日のブログの続きです。
昨日は犬の自然治癒力を尊重することができるか?を自分に問いかけてもらう機会をつくってもらうためのお話でした。
私たちが今の窮屈な生活を国や地域のルールのものに実行せざるを得ない状況になってしまったのも、そもそも動物の治癒力とか免疫力について考える機会があまりにも遠くなってしまっていたからではないかと反省しています。
だから決められたルールの中で反論をできる人もおらず、マスコミや専門家の走り出したレールに何の考えも反発も反論もできず乗るしかなかったのではないかと…。
※追記と修正はここから
インフルエンザには治療薬が出ているとご指摘いただきました。
勉強不足ですみません。以下に自分で調べたこと追記しておきますが医療について詳しいことはさらに病院で確認してください。
2019年抗インフルエンザ薬として国内で許可されている薬
オセタミブル(商品名タミフル)、ザナミビル(商品名リレンザ)、ラミナミブル(商品名イナブル)、ペラミビル(商品名ラピアクタ)
抗インフルエンザ薬は発症早期に使用すれば入院や死亡のリスクを減らすことができる。
抗インフルエンザ薬によってウイルスの増殖を防ぐことができるためにウイルス価を減少することができウイルス拡散を防ぐこともできる。
以上が私が調べた内容ですが専門的にはまだまだ進んでいると思います。
コロナウイルス治療薬ができるのは時間の問題なのでしょう。
追記ここまで
ワクチンさえできればという声もありますが、ウイルスの型など変化し続けるものなのにどのくらいのワクチンをバクチのように投与しようというのでしょうか。
新型ウイルスに関わらず多くの病気は本来は個々の動物の中にある自己免疫力の作用があって快復に向かいます。
薬や治療はそのサポートでしかなく自己免疫力の作用が起きる自然治癒力は生きることに欠かすことはできないのです。
※もちろん薬がないと始まらない治療もありますので信頼のある薬を上手に活用させていただきます。※
人であっても病気によって状態は様々なのですが、犬の方は人よりももっと自然治癒力に頼っているのが犬の動物らしさです。
さらにどんなに動物の医療が発達したといっても現時点で人と同じ医療行為が受けられるわけではありません。
また動物に対する医療行為の負担というのもの考える必要があります。
さらに動物医療は動物の自然治癒力が働いてこそ効果が訪れることを繰り返しておきます。
動物の自然治癒力を考えるにあたって、自然治癒力の働きについて述べた精神科医の神田橋條治先生のことばをお借りします。
神田橋先生は自然治癒力についてご自身の著書にこのように説明されています。
「いのちは、よくない状態から回復するためのいろいろな方法を、自然にもっているのです。これが自然治癒力です。病気のときには、必ず自然治癒力が働きます。いのちが病気をなんとかしようとするからです。」
神田橋條治先生の著書「精神養生のコツ」から転載
すごくわかりやすい言葉ですね。
動物はみんな自分の心身の不具合を改善させるための方法を自然に持っているということです。
人も自然治癒力を持っていますし、犬は人以上に高い自然治癒力を持っています。
ところが犬が具合が悪い、虫に刺されたようだ、といったときに犬の自然治癒力を頼りにする飼い主は少なくなりました。
同じように私たち人の方も、すぐに病院に行くようになりました。
病院に行くことがいけないといっているのではありません。
適切な時期にきちんとした治療を受けることができる日本の医療は本当にありがたく、活用すべきです。
動物病院にしても世界でも最先端の医療が受けられる日本の動物病院の処置は大変優れたものだと思います。
そうであっても自然治癒力がなければ病院があっても動物は治癒しないのです。
犬の自然治癒力はなぜ注目されないのでしょうか。
次回はこの続きをおはなしします。
※追記8月16日
人間の医療の発達は本当に素晴らしいものがあります。
IPS細胞の作製に成功してノーベル賞を受賞された山中教授の講演の中ではその課程で犬たちが実験動物として使われたことも話しておられました。
もちろん犬の前にはたくさんのマウスが利用されています。
私たちの使っている薬やワクチンの開発には動物たちの命の積み重ねがあった上での宝ものなので、ここぞという時にはぜひ活用していただいてお医者様にも動物たちにも感謝したいと思います。
そしてその分を生きる時間として増やしたのなら、何かのお役に立てるよう今日も生きなければなと気持ちも引き締まります!

<犬・自然のこと>犬の自然治癒力を信じるのが難しい理由
今日のブログのタイトルを見て驚かれた読者の方に先に説明します。
もちろんわたしは犬の自然治癒力を信じてます。
もう少し正しくいうと、犬の自然治癒力が発揮されるために飼い主としてできることをしたいと思いそれをするために博多駅の近くから唐津市の山の中にドッグスクールを移転させました。
「犬の自然治癒力を信じるのが難しい」とタイトルにいれたのは、現在では圧倒的にこちらに考えをする飼い主が増えていると感じるからです。
山の中で犬といっしょに山歩きやトレッキングクラスと楽しいこともたくさんあるときに、反して山の野生の生物たちに刺されたり咬まれたりする危険も伴います。
虫に刺されるのは犬よりもヒトの自分の方が回数は多く、毎日の草刈りの時間であってもどこか1ケ所はブユ、アブ、蚊などのとび虫にやられてしまいます。
ななやまに移転したときに最初にブユに顔を刺されたときは大変腫れて泣きそうになりました。
痛み、かゆみ、腫れ、どれも苦痛の体の反応ですが、薬が得意でないわたしは自然素材の中から自分にあいそうなものを探し、やっと「びわの葉エキス」が炎症を抑えることを知って今も愛用しています。
一方で犬の方はもブヨなどに腹部をさされたり、ダニを体につけたりといろいろと攻撃を受けていました。
一番自分が見守ることのできた愛犬オポの自然生物との付き合い方や、虫に攻撃を受けたあとの治癒力を観察していくことで犬の治癒力の高さを知ることができました。
同時に手を出し過ぎることで起きる犬への負担についても学びました。
しかしオポは山に移転して山という自然あふれる環境の中で毎日を過ごすことでその能力を高めていったのです。
都会に住む犬はたまに山に来たとしてもオポのように山犬に体を変えるわけでもなく日々の環境によるストレスも多いのです。
だから今では予防としてできることはある程度するが過剰にはすすめない、そして犬の自然治癒力がどういうものなのかを飼い主自身が興味関心を持って真剣に学び知っておくことの方が大切だと思っています。
現在では人が直面している正体のわからないウイルスがいます。
検査をした方がいいという人、する必要のないという人
ワクチンをした方がいいという人、しない方がいいという人
意見はそれぞれに分かれていて、自分がどう考えるのかを問われています。
SNSの普及でテレビでいうからすべて正しいという価値観がなくなった分、見極める個人の力が試される時代でもあるのです。
犬の自然治癒力を信じるのか、もし自然治癒力を信じるのなら自分の中にある自然治癒力ってなんだろうとまずは自分の内側を見つめる機会をつくることをおすすめします。
明日はこの続きで、わたしよりもずっと説得力のある先生の書籍からご紹介しますのでお楽しみに!

<日々のこと>お盆に思う出会った犬たちのこと
今年はお盆のお墓参りも自粛されているようで七山でも県外ナンバーの車を見る機会がありません。
一方で移動している車は大変多く、お盆に実家には帰らないけど遊びに出かける人々は多いようです。
こんな滑稽な風景を見るようになるとは、仏様たちはわたしたちのことをどんな風に見ているのかなと思います。
お盆に亡くなった犬たちが本当に戻ってくるかどうかよりも、大切なのは自分の心の中で死者と語り合う時間が持てるかどうかだと思います。
都会の中ではなかなかできない習慣が自然の空気漂う七山では得られることを感謝しています。
お盆までには間に合わなかった山の手入れをしながら、いっしょに歩いた犬たちのことをなつかしく思い出す時間が私のお盆です。
そしてなによりも思い出すのはもちろん自分と暮らした犬のオポのこと。
たくさんのいっしょに過ごした時間があってまだ覚えていることがあります。
時間がたつと思い出すことが少なくなっていって思い出も空気となる時間がくるのでしょう。
生徒さんにいただいたお盆のお飾りを写真の前に飾りました。
そのオポの本当のお墓の上のしだれ梅の枝を預かり中の犬ちゃんがひっぱって遊んでいます。
オポだったらどうやってこの犬ちゃんと向き合ってくれただろうか。
自分には到底できないことだけど空想することで何かのヒントを探している自分がいます。
それだけたくさんのことを私に残してくれたオポ、自分の本当の犬の先生でした。
グッドボーイハートは一子相伝。
オポから私へと、そして次に続くのは誰なのか楽しみです。
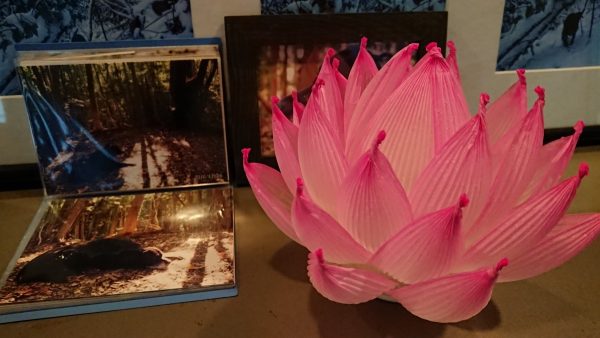

<お預かりクラス>人の作業をお手伝いしようとする本当の服従性をみせる犬ちゃん
福岡から唐津市七山まで車で約一時間。
標高は500メートルもない七山ですが地形が「風の谷」なので気温は唐津市より3度は低いです。
コンクリートの丘の福岡市と比較すると5度くらいは低いでしょう。
朝露、夜露で地面が濡れていることから夜は気温が下がっていることがわかります。
この季節のお預かりクラス利用の犬たちの目的は、暑い都会からの避暑地代わりといったところでしょうか。
今回もまた急遽お預かりクラスのご希望がありバタバタと七山に移動してきました。
犬が山で過ごす機会は生涯を通して本当にわずかしかありません。
貴重な体験をさせたいと欲が出てしまい、グッドボーイハートの犬たちがお預かりクラスを利用するときにはできるだけ山で預かりたいと調整をはかります。
今回の犬ちゃんはお預かりにとても慣れていて、ほとんどマイホーム的に七山グッドボーイハートで過ごしています。
私でもダンナくんでもどちらのいうこともちゃんと従い、この家のルールも習得しています。
草刈りだ、薪の整理だ、テラスの片づけだ…と作業が続くのですが、私たちのそばでお手伝いをしようと張り切っています。
草刈り機のコードが絡まってしまい、そのコードの絡まりをとく作業をしていたところ犬ちゃんがやってきてコードを噛もうとします。
ほとんど作業を中断させる行為になるのですが、気持ちはよくわかるので「えらいね、ありがとう」といいながら手早く済ませます。
鎌を持って草刈りをしているときには見張り台のような木の上から周囲を見渡しており、やはり作業を手伝うとしてくれます。
こうした犬は当然のことですが人に対する服従性がきちんと身についています。
それは叱ったりほめたりすることで身に付いたものでもないし、犬が善悪を判断しているわけではありません。
犬は人の活動に興味を示しその活動に自分の立場で関わろうとしているだけです。
こうした関係が本当に楽しく素晴らしく犬としてやりがいのあることですが、ペットとしての生活には活動という場面もほとんどありません。
都会では屋外での活動が散歩だけなので、散歩を充実させることがとりあえずの活動なのです。
でも、お休みのときには野外に出て本当の活動をして関係を深めてください。
ドッグランで犬を走らせてそれを見ているだけでは、いっしょに活動したとはいえません。
とりあえず犬との山歩きから始めましょう。
GOTOダメとかいろいろありますが、犬の生涯は短いのですからそこのところをお忘れなく。




