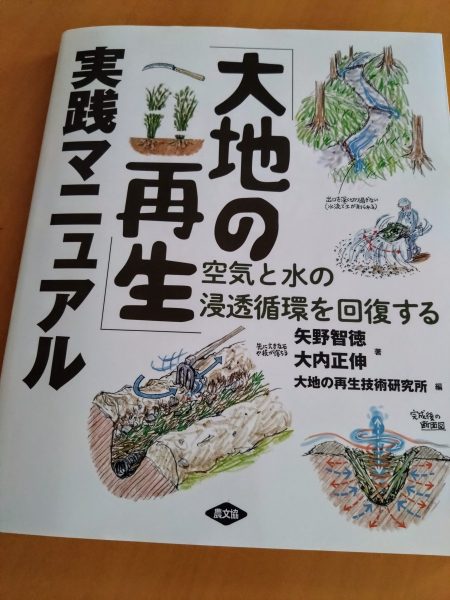オンラインクラスの受講について
福岡にもたくさんあるドッグスクールは、どのスクールも「人と犬の豊かな暮らし」を目指していると思うのですが、スクールによって価値観や特色が違います。グッドボーイハートの特徴あるクラスといえば、自然と関わるクラスです。犬と山歩きをするトレッキングクラスや自然環境の中で活動するお預かりのクラスがあります。
また当校の特徴として、どちらかというと犬の立場にたって考えるという姿勢を大切にしています。犬の習性や本能という機能ができるだけ発揮されることが犬の幸せにつながり、犬と人の関係を深めてくれると考えているからです。
このような特徴に共感して下さり当校でのクラス受講を希望される方からのお問い合わせをいろんな地域からいただくのですが、時には本州や海外といったこともあります。
遠方の方が最初に受講できるのはオンラインクラスです。オンラインクラスでは環境整備や犬の習性などについての座学はお話しできるものの、大切な犬との接し方やリードの使い方などを上手く伝授することができません。
本州でオンラインクラスを受講するロクちゃん
実は数ケ月前にも、本州にお住まいの飼い主からオンラインクラスの受講依頼を受けたのですが、上記の理由からカウンセリングは受講できるがトレーニングについては地元のトレーナーを探すことをおすすめし、その上でカウンセリングクラスを受けていただきました。しかし、カウンセリングクラスを受講後にやはり当校でトレーニングを受講したいというご連絡を受けたため、再度、手技については対面でないと説明が十分にできないことをお伝えした上でオンラインクラスをスタートしました。
そして、クラスは進行してきたのですが、予想したとおりリードの使い方のところでお互いにフラストレーションを抱える時がやってきました。受講生はもともとバンに乗って旅行をしたり山歩きをしたりするのが趣味だとお聞きしていたので、「夏休みにロクちゃん(受講生の犬ちゃんの名前)と一緒にお出かけをされるのならぜひ九州にいらしてくださいね」と軽く口にしたのですが、なんとその後すぐに「九州行きます。」と連絡があったのです。
ロクちゃんのお預かりクラスと初めての山歩き
5月の連休終わりにロクちゃんは飼い主さんと一緒にオポハウスに到着しました。今回受講するクラスはお預かりクラスとトレッキングクラス、そしてクラスの途中でリードの使い方について説明することになりました。お預かりクラス中は飼い主さんたちは九州の山へと向かうという計画です。この期間に数頭の犬達がいましたが、どの犬もオポハウスを定期的に利用している犬だったので対面はスムーズに進みました。

右がロクちゃん、左がジェイ、手前が菜々ちゃん、オポ広場にて
ロクちゃんは兄弟犬と少し関わったことがあるものの、地域では対面できる犬がおらず久しぶりに犬と交わることになりました。生後6ケ月で子犬から成犬に向かっていく変化の多い時期ですが、犬と強く関わりたいという欲求の高いロクちゃんにとっては一日はあっという間に過ぎたのではないかと思います。

手前がロイくんで奥がろくちゃん
お預かり期間が4日目になりやっと落ち着いてきたなというときに、お迎えの飼い主さんが到着しました。
最終日は予定されていた平日のプチグループトレッキングクラスに参加しました。まだリードを上手く使えない状態での参加となりましたが、山歩きに慣れていてバランスの取れる飼い主さんでしたので、なかなかいい具合にロクちゃんとの歩行が進みました。

グループトレッキングに参加したロクちゃんと飼い主さん
お預かり中の犬とのコミュニケーションの最中にフセの練習や止めといったら止めるなどの抑制の練習も自然としていたことも、自制を働かせる練習として効果があったようです。
トレッキング後は一緒に山歩きをしたグッドボーイハート生たちとお話をしたことで、ロクちゃん飼い主さんは「心が軽くなりました」と言われました。共に歩む仲間がいること、共感できる仲間がいることは新しいことを学んでいくなかでとても大切なことです。
今はインスタグラムといったお互いの活動を紹介する場もありますので、自慢しあうのではなく励まう道具としてSNSを活用し、お互いに学びを深めていかれるでしょう。

ヤギのアールとゼットを見つめるロクちゃん(黒い犬)
グッドボーイハートで学べること
今回のようなケースは例としては少ないです。やはり地域のスクールの方が利便性が高まり参加する頻度が高くなります。ドッグスクールは他のいろんな学びの学校と同じように、一度来て終わりというものではなく、長く続けて学ぶほど身に着くものは多くなります。しかし、こうして遠方からオポハウスに来て下さった飼い主さんは、その行動力とその行動を起こすための原動力を発揮することで、きっと人以上の多くのものを持ち帰られたことと思います。
お預かり期間中に毎晩、こちらから送信した報告と写真や動画を見て、ロクちゃんの今までには見たことのない行動や変化に驚かれていました。預かり期間で犬たちが経験したことは犬にとっての学びにはなります。楽しいことだけでなくむしろ上手くいかないことや我慢を強いられること、犬と犬の関わりは表面的でないので対立は常に起きているからです。でもクラスを通して変化を促していきたいのは犬というよりも飼い主の方なのです。
例えば、お預かり期間中の動画を見て、自分が思っていた犬とは違うということを知ることや、自分が犬についてまだ何も知らないのだということに気づくことが一番大切なことです。その上で、犬に社会的な、特に犬と犬が接するという社会的な活動を与える習慣や環境がなければ、是非定期的に預かりクラスを利用していただきたいと思います。
犬と山を歩くクラスは、飼い主さんが犬と自立して活動をするためのきっかけを作るものです。またその上で、集団で山歩きをする仲間や環境が身近になければ当校のグループクラスでその活動を補っていただければと思います。自然の中での集団活動は犬には刺激ある活動となり、結束すればするほど引き締まるものです。そんな引き締まる経験が犬には良い刺激剤になります。
車もクレートも苦手な状態で本州から来てくれたロクちゃんと飼い主さんたちと貴重な時間を過ごさせていただき感謝いたします。この学びをまた次の学びへとつなげていきます。
追記になりますが、ロクちゃんの飼い主さんはカヌー犬の岳(がく)ちゃんに憧れて、という話を聴きました。わーと私が大きく反応すると「ご存じですか?」と聞き返されてしまいました。
ご存じもなにも、冒険家の野田知佑さんのカヌーに乗っていたミックス犬の岳ちゃんは犬大好き少女だった私にとっては憧れの存在でした。物凄く懐かしく、椎名誠先生の探検隊シリーズでアウトドア体験に憧れた幼少のときの記憶がふんわりと浮かんで消えました。
ロクちゃんの飼い主さんはものすごく若い世代なのに、時代を問わずに影響を与えている岳ちゃんの存在の素晴らしさに感嘆しました。ロクは麓、山麓からついた名前だそうで納得します。ロクちゃんはとても素敵な飼い主さんと巡り合ったのだなと深く思いました。いつの日かの再会を楽しみにしています。

手前がロクちゃんで奥がジェイ









 上の写真はまだ重機があり、Jにはロングリードを付けています。
上の写真はまだ重機があり、Jにはロングリードを付けています。